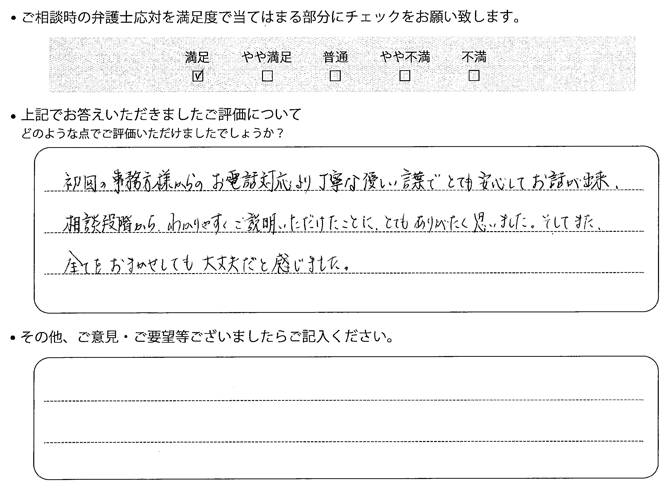休業損害における稼働日数の影響

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
この記事でわかること
休業損害の計算をする際に、“稼働日数”という言葉が出てきます。稼働日数は、休業損害の計算結果に大きな影響を与えかねない重要な根拠として用いられることもあるので、特に会社員などの給与所得者の方にとっては重要視すべきトピックといえます。 そこで本記事では、休業損害の「稼働日数」に着目し、稼働日数が基礎収入額の計算にどのように影響してくるのかだけでなく、休業損害証明書を書く際の注意点や保険会社の主張と交渉する際のポイントなどについても具体的に解説していきます。 本記事にて、休業損害の細かい点までしっかりと理解を深めていきましょう。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
交通事故に遭いお困りの方へ
目次
休業損害の稼働日数とは
稼働日数とは、“休日や祝日を抜いた実際に働いた日数”のことで、休業損害は交通事故の怪我が原因で働けなかったことによる減収を補償するものです。 休業損害は基本的に「基礎収入額×休業日数」で計算されますが、そもそも休業損害の計算に用いる算定基準には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準(裁判基準)の3つの基準があり、各基準によって基礎収入額の扱いが異なります。 自賠責基準では、「一律1日あたり6100円」が基礎収入額として扱われるのに対して、弁護士基準では「事故前3ヶ月の給与合計額÷当該期間の実稼働日数」で算出する考え方が取り入れられています。任意保険基準は各保険会社によって基準が異なるものの、ほとんどの保険会社で「事故前3ヶ月の給与合計額÷90日」の算出方法が取られている実情です。
基礎収入額は稼働日数を用いて算定すべき
休業損害における基礎収入額の主な算定方法は、次の2通りです。
- ① 【任意保険基準】事故前3ヶ月の給与合計額÷90日
- ② 【弁護士基準】事故前3ヶ月の給与合計額÷当該期間の実稼働日数
休業損害の交渉においては、➁の弁護士基準の算定方法の方が高額となることから、保険会社の大半は①の算定方法を用いた休業損害を主張してきます。 しかし、被害者の方が交通事故によって被った損害に対する適切な補償を受け取るためには、➁の弁護士基準の算定方法、つまり、稼働日数を用いた算定方法が採用されるべきといえます。 なお、自賠責基準の場合は、一律6100円の基礎収入額と決まっています。 ※令和2年4月1日より前に発生した交通事故の場合は、旧基準が適用され一律5700円となります。 「休業損害は1日いくらになるのか?」などの具体的な計算方法に関しては、以下のページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
【ケース別】休業損害の稼働日数の数え方
休業損害の計算を行う際には稼働日数が重要となることがわかりましたが、どのように稼働日数を数えればよいのか悩まれる方もいらっしゃるでしょう。 そこで次項では、ケース別で稼働日数の数え方を解説していきます。
有給を取得した日は実稼働日数に含まれる?
有給を取得した日も、実稼働日数に含まれます。 なぜなら、有給は実際には仕事をしていませんが、給与は支給されているからです。 稼働日数は、“給与が発生する対象となる日”のことを指すため、有給を取得した日であっても給与が発生していれば、実稼働日数に含まれることになります。 以下のページでは、有給休暇を使用した場合の休業損害の請求方法について解説しています。 ぜひあわせてご参考になさってください。
合わせて読みたい関連記事
土日・休日出勤は実稼働日数に含まれる?
休日出勤に対する手当が支給されている場合は、土日・休日出勤した分も実稼働日数に含まれます。 対象となる日が実稼働日数に含まれるかどうかは、“対象日に給与が支給されるか否か”がポイントとなります。給与が支給される日は、基本的に実稼働日数に含まれます。そのため、もともと休業日である日に出勤して給与が発生しないような場合は、当然実稼働日数に含まれません。
治療のために遅刻・早退したら休業損害はどうなる?
治療のために遅刻・早退した場合も、休業損害として請求することができます。 しかし、休業損害の計算において支払われなかった給与が半日分なのか、あるいは数時間分なのかなど、より細かく算出していくことになるため、休業損害証明書にその旨を具体的に記載する必要があります。 そのため、勤務先へは遅刻・早退について具体的に記載してもらうようにお願いし、証拠資料として半休や早退したことを記録に残しておくとよいでしょう。 また、怪我の程度、症状、通院方法、日数等によっては、会社を休んで病院に行くことが不相当と判断される場合もあります。たとえば、怪我がほとんど治ってきているにもかかわらず、毎日半休の午後休を取り整骨院に行っている場合などは、「会社を休む必要がない」と判断されて休業損害を請求できないおそれがあるため、注意が必要です。
自宅療養した日は稼働日数に含まれる?
治療ではなく自宅療養のために休業した日が休業日数に含まれるかどうかは、「医師により自宅内での安静加療の指示があったかどうか」によって判断されます。医師からの指示があった場合は、休業日数として扱われる可能性が高い一方、自己判断による場合は、当然に休業損害が払われるものではないので、注意が必要でしょう。 怪我の程度や業務の内容等により休業することが相当である場合には、休業損害を請求できますが、仕事を休んだにもかかわらず休業損害が認められないケースもあります。 例えば、軽度のむちうちで、すでに軽快しているにもかかわらず、自宅療養として自己判断で仕事を休む場合には注意が必要でしょう。
合わせて読みたい関連記事
休業損害における給与所得者の基礎収入額の計算方法
任意保険基準と弁護士基準の算定方法で、基礎収入額にどれくらいの差が生じるのか、実際に計算して違いを確認してみましょう。
【例】月給30万円の会社員(給与所得者)の方が、治療のため20日間仕事を休み、事故前3ヶ月間の実稼働日数(勤務日数)が57日間であった場合
《任意保険基準の休業損害》
【基礎収入額の算定方法】事故前3ヶ月の給与合計額÷90日 基礎収入額:90万円÷90日=1万円 休業損害=1万円×20日=20万円
《弁護士基準の休業損害》
【基礎収入額の算定方法】事故前3ヶ月の給与合計額÷当該期間の実稼働日数 基礎収入額:90万円÷57日=1万5800円 休業損害=1万5800円×20日=31万6000円
それぞれの算定方法で計算してみると、弁護士基準の方が10万円以上も高額となることがわかります。 休業損害の請求をする際には、弁護士基準の算定方法を用いることが大切です。
給与所得者以外の基礎収入額の計算方法
主婦(主夫)や自営業といった、いわゆる給与所得者以外の方々の基礎収入額の算出においては、稼働日数の考え方はあるのでしょうか? 結論としては、国の賃金に関する統計である“賃金センサス”や“確定申告書”を365日で割った金額を基礎収入とすることが多いため、稼働日数が関連してくる可能性は低いといえます。 詳しくはこちらで解説していますので、ぜひ参考になさってください。
合わせて読みたい関連記事
休業損害証明書を書く際の注意点
休業損害を請求するためには、「休業損害証明書」が必要となります。 休業損害証明書の内容に不備があると、相手方保険会社から休業損害が正しく支払われないおそれがあるため、注意が必要です。 主な注意点は、次のとおりです。
- 休業した日にちや休業日数を正確に記入してもらう
- 有給休暇、半日休暇、遅刻、早退について、時間を細かく正確に記入してもらう
- 休業損害証明書の作成者や勤務先の社判などを漏れなく捺印・記入してもらう
- 休業損害証明書に記入するマーク(例:欠勤→〇、有給休暇→◎など)を間違えない など
これらの注意点を気に掛けることで、休業損害を漏れなく相手方保険会社に請求することができます。 また、勤務先から完成した休業損害証明書をもらった後は、相手方保険会社に提出する前に自分でも内容を確認して、不備があれば追記・訂正を再度勤務先へ依頼するようにしましょう。 さらに具体的な休業損害証明書の書き方については、以下のページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
保険会社の主張と交渉する際のポイント
“正当”で“納得できる”金額の休業損害を受け取るためには、基礎収入額を稼働日数で算出することが不可欠となってきます。 しかし、実際に示談交渉を進めていくと、自賠責基準の計算方法を根拠として基礎収入額を90日で算出した休業損害を提示してくる保険会社がほとんどです。提示内容について、いわば素人である被害者が交渉を試みても、根拠を求められるなど相応の負担・労力がかかりますので、精神衛生上良くないでしょう。 こうした交渉は、交通事故事案の実績を重ねている弁護士に依頼すべきです。保険会社を相手に、どういった立証資料が必要なのか、適正額はいくらなのかといった事柄を丁寧に精査し、被害者に代わって交渉を進めていくことができます。
稼働日数で算定した休業損害が認められ、約455万円の賠償金を獲得できた事例
ご依頼者様は、走行中に対向車線からセンターラインオーバーしてきた相手方車両に衝突され、頚椎捻挫を受傷しました。約半年以上通院を継続しましたが、頚部痛や右上肢のしびれ等の症状が残存したため、今後の対応について当法人にご依頼いただきました。 まずは、残存した症状について後遺障害等級認定の申請手続きを行い、後遺障害として14級9号の認定を得ることができました。 その後の賠償交渉では、相手方保険会社の回答は当初、休業損害の基礎収入額の計算は90日割りで算定され、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益についても裁判基準を大きく下回る金額でした。 しかし、弁護士にて休業損害の基礎収入額の計算は「稼働日数割りが相当である」と粘り強い交渉を続けた結果、こちらの主張が認められました。 その結果、最終的に自賠責保険金を含め、約455万円にて示談することができました。
休業損害の稼働日数についてご不明な点があれば、弁護士にご相談ください
休業損害の基礎収入額は、「90日で割る場合」と「稼働日数で割る場合」があります。 相手方保険会社は、休業損害の計算方法として「90日で割る場合」を前提に示談交渉を進めることが圧倒的に多く、稼働日数に基づき計算すべきであることを、そもそも理解していない場合もあります。自分が想定していたよりも休業損害額が少なく、この金額では今までの生活ができないと困られる方もいらっしゃるでしょう。 弁護士であれば、確かなる根拠をもとに少しでも被害者の方に有利な計算方法で休業損害を算出して請求していきます。また、休業損害に限らず、交通事故全般に関する交渉を任せることができ、肉体的・精神的負担を和らげることができます。 弁護士法人ALGでは、交通事故に関する問い合わせ窓口を設けています。受付職員がお話を伺いますので、いきなり弁護士への相談を躊躇される方でも安心してお話いただけます。休業損害や稼働日数に関することやその他不安なご状況について、ぜひお気軽にご相談ください。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
交通事故に遭いお困りの方へ


交通事故事件の経験豊富な
弁護士が全面サポート
弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。