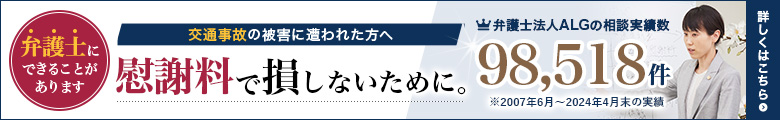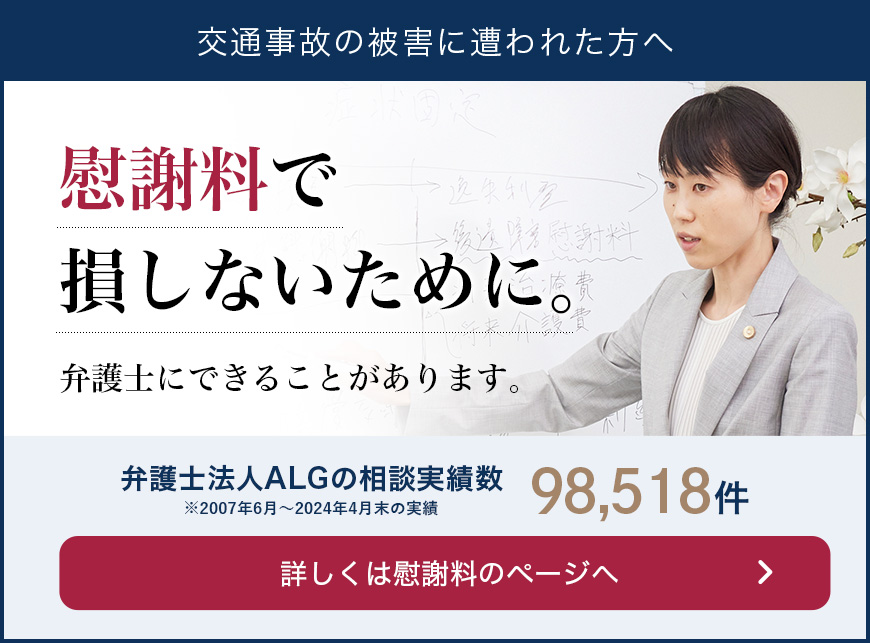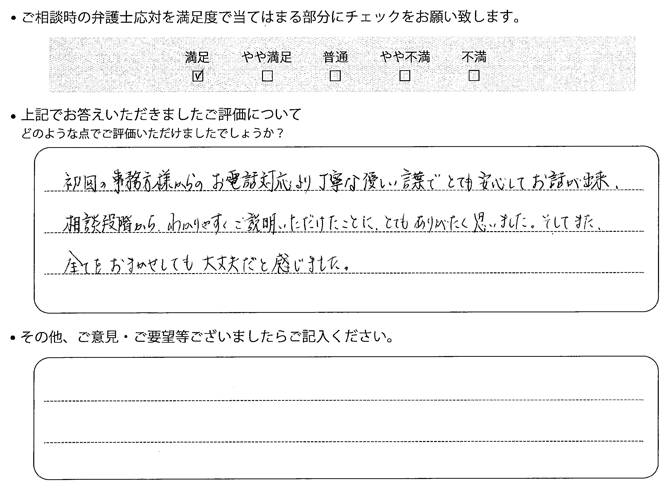交通事故の慰謝料はリハビリでも支払われる?計算方法や知っておくべき注意点

監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治弁護士法人ALG&Associates
交通事故で負った怪我の症状の改善を図るためにリハビリをする場合、リハビリでの通院分も慰謝料を請求できるのか、疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。 結論としては、リハビリも治療の一環として扱われるため、通院慰謝料を請求できます。 しかし、通院期間や通院頻度、リハビリの内容次第では、慰謝料が減額されることがあります。 リハビリを余儀なくされたことについて適正な通院慰謝料をもらうためには、どのような点に注意すべきなのでしょうか。本記事で詳しく解説していきます。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
0120-630-807
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
交通事故に遭いお困りの方へ
目次
交通事故のリハビリ期間も入通院慰謝料はもらえる
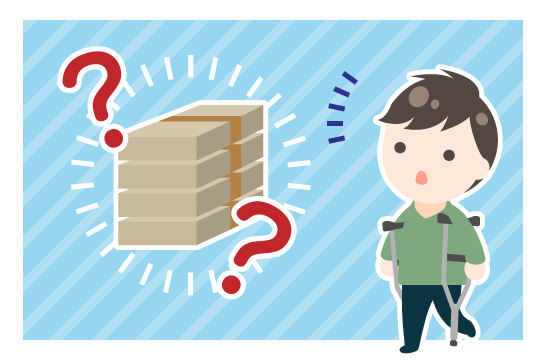
リハビリ期間であっても、問題なく入通院慰謝料をもらうことができます。 なぜなら、入通院慰謝料とは「事故で負った怪我の治療のために、入院や通院を強いられたことに対する慰謝料」であり、リハビリのための通院も“治療のための通院”とみなされるからです。 リハビリは、交通事故による怪我等が原因として生じる身体の不自由を改善するために行われるものです。リハビリによって症状の改善が期待できるのであれば、まだ症状固定(治療してもしなくても症状が改善も悪化もしないこと)していないと考えられるため、リハビリ中も治療期間として扱われます。 そのため、リハビリ中は通院に伴う精神的苦痛に対する慰謝料として「通院慰謝料」を受け取ることができ、純粋な治療について支払われる慰謝料とリハビリについて支払われる慰謝料の金額に違いもありません。
症状固定後のリハビリは慰謝料がもらえない
症状固定後は治療が終了したとみなされるため、基本的にそれ以降のリハビリ費を含む治療費や通院慰謝料を受け取ることはできません。 自社の負担を軽くしたい保険会社は、なるべく早く治療費や通院慰謝料の支払いを打ち切るために症状固定するように提案してきますが、症状固定の時期を判断するのは医師です。そのため、症状固定の時期は医師と話し合って慎重に決めるようにしましょう。 症状固定の時期が実際の症状に見合わない場合、適切な後遺障害等級が認定されず、十分な後遺障害慰謝料を受け取れないおそれがあります。怪我が完治せずに後遺症が残ってしまった場合には、今後のためにも適切な後遺障害等級認定を受けるべきといえます。 そのためには、保険会社からの提案に安易に同意せず、自分に本当にリハビリが必要かどうか、よく医師と相談することが大切です。
合わせて読みたい関連記事
入通院慰謝料と併せてもらえる賠償金
入通院慰謝料と併せて受け取れる賠償金には、次のようなものがあります。
- 治療費、入院雑費、治療用装具費
- 通院交通費、駐車代
- 付添看護費
- 休業損害
- 後遺障害慰謝料
- 後遺障害逸失利益 など
<治療関係費>
治療を行うために必要となった治療費そのものや入院時必要となったアメニティなど
<通院交通費>
通院のためにかかった交通費や駐車代など
<付添看護費>
付添人に生じた交通費、雑費、その他付添看護費に必要な諸費用など
<休業損害>
治療のために仕事を休まなければならず減ってしまった収入に対する補償
<後遺障害慰謝料>
後遺障害が残ったことで今後も受け続ける精神的苦痛に対する補償
<後遺障害逸失利益>
後遺障害を抱えることで、本来得られるはずだったのに得られなくなってしまった収入に対する補償
リハビリでもらえる入通院慰謝料の計算方法と相場
交通事故の慰謝料を計算するための算定基準には、次の3つの基準があります。
| 自賠責保険基準 | 被害者に最低限の補償をすることを目的とする、自賠責保険による補償額の算定基準 |
|---|---|
| 任意保険基準 | 自賠責保険基準に準ずる、それぞれの任意保険会社により異なる補償額の算定基準 |
| 弁護士基準 | 3つの基準のうち最も高額になる、裁判の際等に弁護士が補償額の算定等に使用する基準 |
3つの基準は、自賠責基準 ≦ 任意保険基準 < 弁護士基準の順に高額になっていきます。 弁護士基準がもっとも高額となる基準であるため、損害賠償請求時には弁護士基準を用いて計算するのが望ましいでしょう。 では、各基準によってどれくらい相場に差が生じるのか、例を使って表をみていきましょう。 ※任意保険基準は各保険会社で算定基準があるため、割愛させていただきます。
【例】骨折によるリハビリで通院期間3ヶ月、実通院日数30日の場合
下表で該当する通院期間をみてみると、自賠責基準は25万8000円となります。骨折は重症とみなされるため、重症の弁護士基準をみてみると、73万円が入通院慰謝料の相場となっています。表をみれば、弁護士基準の慰謝料相場の方が自賠責基準の慰謝料相場よりもはるかに高いことがわかります。
| 通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 軽症/重症 |
|---|---|---|
| 1ヶ月(実通院日数10日) | 8万6000円 | 19万円/28万円 |
| 2ヶ月(実通院日数20日) | 17万2000円 | 36万円/52万円 |
| 3ヶ月(実通院日数30日) | 25万8000円 | 53万円/73万円 |
| 4ヶ月(実通院日数40日) | 34万4000円 | 67万円/90万円 |
| 5ヶ月(実通院日数50日) | 43万円 | 79万円/105万円 |
| 6ヶ月(実通院日数60日) | 51万6000円 | 89万円/116万円 |
しかし、慰謝料の算定をもう少し簡単に早く算出したいものです。 そのような場合には、以下の【自動計算ツール】をぜひご活用ください。 必要な項目をご入力いただくだけで、損害賠償金額の目安をみることができます。
自賠責基準の算定方法
自賠責基準の入通院慰謝料を求める計算式は、次の2つです。
① 日額4300円×入通院期間
② 日額4300円×(入院日数+実通院日数)×2
※なお、2020年3月31日以前の事故は日額4200円となります。
①と②を計算し、金額の少ない方が入通院慰謝料として採用されます。 では、以下のケースをモデルに考えてみましょう。
【例】骨折によるリハビリで通院期間3ヶ月(90日)、実通院日数30日のケース
このケースを①と②の式に当てはめると、
① 日額4300円×90日=38万7000円
② 日額4300円×30日×2=25万8000円
となります。
金額が少ない方は②となるため、25万8000円が入通院慰謝料として採用されることになります。
このように、自賠責基準の入通院慰謝料を算定する際には、「治療期間」と「実通院日数(実際に通院した日数)」がポイントとなります。また、受傷した怪我の程度によって日額が変わることはなく、一律4300円となります。
弁護士基準の算定方法
弁護士基準の入通院慰謝料は、慰謝料算定表にあてはめて計算を行います。 むちうちなどの、レントゲンやMRI検査に異常が認められない怪我は「別表Ⅱ」の軽傷用を使用し、骨折などの比較的重症な怪我には「別表Ⅰ」の重傷用を使用します。 では、以下のケースをモデルに考えてみましょう。
【例】骨折によるリハビリで通院期間3ヶ月(90日)、実通院日数30日のケース
① 骨折のため、重傷用である「別表Ⅰ」の表を見ます。 ② 入院はしていないため、通院期間に着目します。 通院期間が3ヶ月であることから、【通院3月】の箇所に書かれた数字をみます。 ③ 「73」と書かれているため、例のケースの相場は73万円となります。
| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通院 | AB | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 |
| 1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |
| 2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |
| 3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |
| 4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |
| 5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |
| 6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |
| 7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||
| 8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||
| 9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||
| 10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||
| 11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||
| 12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||
| 13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||
| 14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||
| 15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
なお、月数は暦に関係なく30日間を1月と考えます。 (例)60日間の治療期間の場合➡ 月数は「3月」となります。 また、ギプスをつけての自宅療養期間や入院待機期間については、入院日数に含めます。
交通事故のリハビリで適正な慰謝料を受け取るための注意点
リハビリも治療の一環であり通院慰謝料の対象ですが、適正な慰謝料をもらうためには、次のような注意点を念頭に置いて適切に対応することが大切です。
- ① 転院する場合は事前に相手方保険会社に伝えること
- ② 整骨院へのリハビリ通院は医師の許可を得ること
- ③ 保険会社によるリハビリ費の打ち切りに安易に応じないこと
- ④ 適切な頻度で通院・リハビリすること
- ⑤ リハビリの内容にも気を付けること
- ⑥ 健康保険の立て替えは150日ルールに注意すること
では、それぞれの注意点について詳しく解説していきますので、しっかりと理解を深めていきましょう。
①転院する場合は事前に相手方保険会社に伝える
転院の際には、事前に相手方保険会社へ連絡を入れる必要があるため、忘れないように注意しましょう。 通常治療費の支払いは、相手方保険会社が病院とやり取りし、被害者に立替えが生じないように手続きすることが一般的です。これを「一括対応」といいます。 相手方保険会社へ連絡せずに転院した場合、一括対応の手続きを行うことができないため、治療費の支払いが遅れたり、場合によっては治療費の支払いを否認されるおそれがあります。 また、「通院先の医師に紹介状を書いてもらうこと」や「相手方保険会社に開示する診断書には【転医】と記載してもらうように医師へ伝えること」が必要です。こうすることで、相手方保険会社から転院について承諾を得やすくなります。 転院する際の注意点について、詳しくは以下のページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
②整骨院へのリハビリ通院は医師の許可を得る
最初から整骨院にしか通院していなかったり、医師の許可なく整骨院へ通院したりした場合には、整骨院へ通院した分の治療費や慰謝料の請求が認められないおそれがあります。 そのため、整骨院への通院を考えている方は、きちんと病院へ通院し治療を受けて主治医に許可を得るようにしましょう。 整骨院の先生は、「柔道整復師」といって柔道整復を行うことができる国家資格をもつ方であるため、医師免許はもっていません。医師ではないことから、施術の必要性や有効性を相手方保険会社から疑われてしまい争いとなりやすいため、注意が必要です。 整骨院治療の注意点について、詳しくは以下のページをご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
③保険会社によるリハビリ費の打ち切りに安易に応じない
相手方保険会社からリハビリ費の支払いについて打ち切りを打診されても、容易に承諾するべきではありません。医師に診断書を書いてもらい提出する等、治療・リハビリの必要性を訴えましょう。
合わせて読みたい関連記事
④適切な頻度で通院・リハビリする
毎日リハビリ通院するなどの過度な通院は、「慰謝料目当ての過剰診療ではないか」と疑われてしまい、相手方保険会社から治療費などの支払いを拒否されることがあります。 通院慰謝料は、通院期間・実通院日数を基準に算定します。 算定の際に重要となるのは、「通院期間」と「通院頻度」です。なぜなら、通院期間が長いにもかかわらず通院回数が少ないと、治療の必要性を疑われてしまうおそれがあるからです。そのため、医師の指示に従い、適切な通院頻度で通院・リハビリを行うことが大切です。 なお、好ましい通院頻度の目安は怪我の具合によって様々ですが、月に1回や1ヶ月以上通院が空いてしまう場合には、治療費の打ち切りやもらえる慰謝料を減額されてしまうおそれがあるため、必ず継続して通院するように心がけましょう。 適切な通院頻度がわからない場合は、初診の際に主治医へ相談するとよいでしょう。
⑤リハビリの内容にも気を付ける
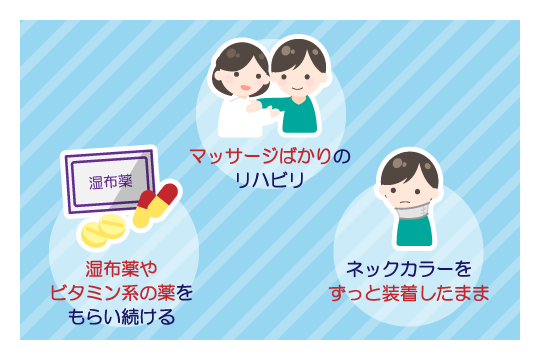
“同じ治療内容を続ける”と「漫然治療」であるとして、治療のための通院と認められないおそれがあります。 漫然治療とは、真摯に症状の改善を目指しているとはいえない治療のことをいいます。 治療内容は主治医が決定するものとはいえ、同じ投薬・治療内容が続いている場合には、漫然治療と疑われないよう、主治医に対し、他の治療方法がないのか相談するなど、積極的に治療に参加しましょう。
⑥健康保険の立て替えは150日ルールに注意
健康保険を使ったリハビリでは、部位ごとに、所定の点数が算定できる日数の上限があります。 つまり、部位によって異なるものの、健康保険が使える期間があらかじめ限られています。 交通事故で行われるケースが多い、運動器のリハビリの場合には、発症から150日が上限とされています。 「リハビリの150日ルール」とは、このような診療報酬算定のルールのことです。 ただし、治療を継続すれば状態が改善することが医学的に期待できる場合等には、例外的に、一定の範囲内で150日を超えてリハビリを継続することが認められます。 もっとも、症状が重い場合には例外として認められる範囲内のリハビリでも不十分ですし、病院としても、経営の観点から例外を認めることに消極的な面があります。
リハビリ期間の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット
リハビリ期間の慰謝料請求を弁護士に依頼することで、次のようなメリットを得ることができます。
- 弁護士基準で適正な慰謝料を請求できること
- 適切な通院頻度についてアドバイスがもらえること
- 後遺障害等級認定をサポートしてもらえること
- リハビリ費用の打ち切りにも対応してもらえること
- 示談交渉などの手続きを一任できること など
弁護士であれば、慰謝料の算定基準のうちもっとも高い金額で算出できる“弁護士基準”にて加害者側の保険会社と交渉に臨むことができます。ただし、慰謝料の計算には多くの専門知識が必要となり、集めなければならない資料や証拠も多いです。そのため、たとえ弁護士基準で計算できたとしても、交渉のプロである保険会社は非常に手強い交渉相手といえるでしょう。 適正な慰謝料を円滑に獲得したいのであれば、弁護士にご相談されることをおすすめします。 慰謝料の請求を一任できるだけでなく、不当なリハビリ費用の打ち切りなどについても加害者側の保険会社と交渉してもらえます。
整骨院にてリハビリされていたが、弁護士のアドバイスにより賠償金約270万円を獲得できた事例
後遺障害等級:非該当 ➡ 14級9号
傷病名:頚椎捻挫
ご依頼者様は、停車中に相手方が運転する車両に追突され、頚椎捻挫を受傷しました。 今後の対応について当法人でご依頼を受けた後は、まず弁護士にて通院状況の確認を行い、ご依頼者様へ適切な通院の仕方についてアドバイスを行いました。 その後、残念ながらご依頼者様に後遺症が残存してしまったため、後遺障害等級認定の申請手続きを行いましたが、初回の結果は非該当でした。 そこで、弁護士にて新たな資料を収集して異議申立てを行った結果、14級9号が認定となりました。 その後の賠償交渉では、副業部分の休業損害や後遺障害慰謝料、逸失利益についてこちらの主張が認められ、最終的に自賠責保険金75万円を含め、約270万円にて示談することができました。
交通事故によるリハビリ期間の慰謝料を適正な金額で受け取るためにも弁護士にご相談ください
リハビリ期間は、“治療のための通院”とみなされるため、リハビリにかかった費用や通院慰謝料の支払いを受けることができます。しかし、加害者側の保険会社の大半が、できるだけ支払額を少なくしたいと考えるでしょう。 適切なリハビリの治療費や慰謝料を受け取るためには、加害者側の保険会社に「リハビリの必要性」について納得してもらうことが重要です。そのためには、交渉のプロである弁護士に依頼されることをおすすめします。 弁護士に依頼することで、弁護士基準で計算した慰謝料を請求することができるため、被害者の方が自ら計算して請求するよりも高額の慰謝料を受け取れる可能性が高まります。さらに、弁護士費用特約に加入されている場合は、加入先の保険会社が定める上限額までは弁護士費用のご負担なく弁護士に交渉を任せることができるため、ぜひお気軽に弁護士へご相談ください。
交通事故被害者専用 相談窓口まずは交通事故の受付スタッフが丁寧にご対応いたします
0120-630-807
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
交通事故に遭いお困りの方へ


交通事故事件の経験豊富な
弁護士が全面サポート
弁護士費用特約を使う場合
本人原則負担なし※保険会社の条件によっては
本人負担が生じることがあります。
弁護士報酬:成功報酬制
※死亡・後遺障害等級認定済みまたは認定が見込まれる場合
※事案によっては対応できないこともあります。
※弁護士費用特約を利用する場合、別途の料金体系となります。